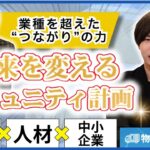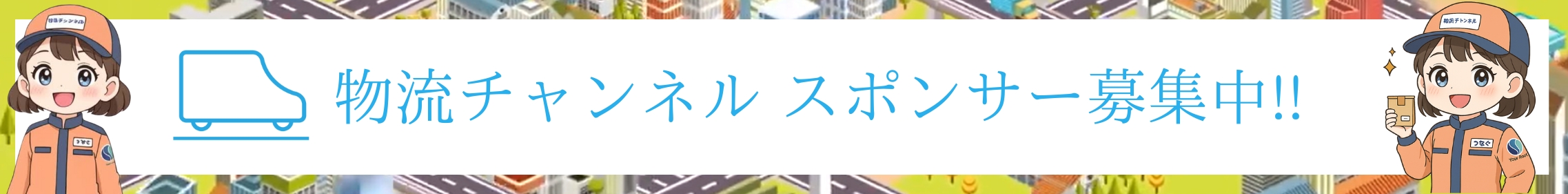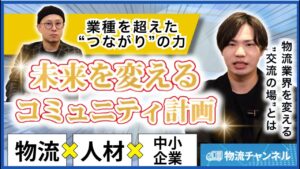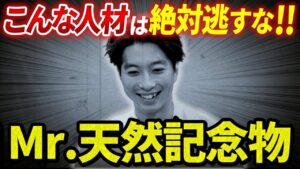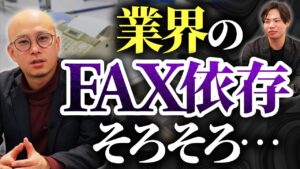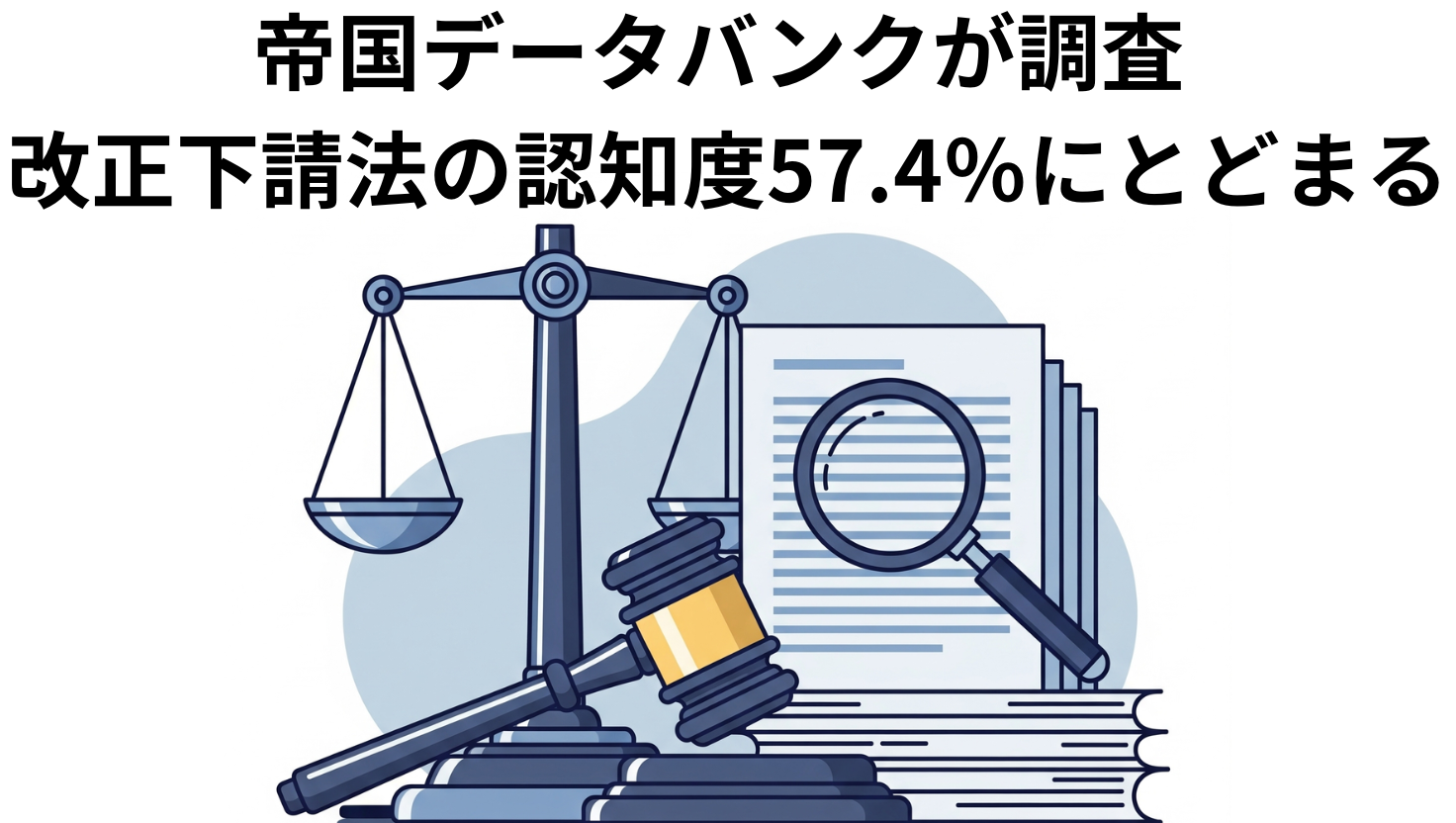
帝国データバンクが調査 改正下請法の認知度57.4%にとどまる
目次
改正下請法の認知度や影響に関する調査
2026年1月1日に施行される改正下請法(下請代金支払遅延防止法及び下請中小企業振興法の一部改正)をめぐり、帝国データバンクは企業3,845社を対象に認知度や影響に関する調査を実施しました。調査では認知度が57.4%にとどまり、中小企業ではさらに低い結果となり、周知活動の強化が必要とされています。受注者側では資金繰りや収益の安定化への期待が高い一方、発注者・受注者ともに業務負担増加への懸念が示されています。
改正下請法とは?約束手形の廃止や価格協議の義務化で取引適正化を目指す
改正下請法(下請代金支払遅延防止法及び下請中小企業振興法の一部改正)は以下のとおりです。
- 手形等による支払いの禁止
- 協議を経ない代金決定の禁止
- 運送委託契約の対象追加
- 従業員基準の追加
- 面的執行の強化
- その他所要の改正
手形等による支払いの禁止
対象取引において、手形払を禁止する。また、その他の支払手段についても、支払期日までに代金相当額を得ることが困難なものは禁止する。
協議を経ない代金決定の禁止対象
取引において、代金に関する協議に応じないことや、協議において必要な説明又は情報の提供をしないことによる、一方的な代金の額の決定を禁止する。
運送委託契約の対象追加
価格転嫁が進みにくいとされていた運輸業を新たに対象業種に加え、取引保護の対象を拡大する。
従業員基準の追加
従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分を新設し、規制及び保護の対象を拡充する。
面的執行の強化
関係行政機関による指導及び助言に係る規定、相互情報提供に係る規定等を新設する。
その他所要の改正
認知度は57.4%、中小企業は54.3%にとどまる
調査によると、改正下請法の内容を「知っている」と回答した企業は全体の57.4%でした。
-
業種別:運輸業71.2%
-
規模別:大企業81.6%、中堅企業85.6%に対し、中小企業は54.3%
-
地域別:最も高いのは近畿(60.2%)、最も低いのは北海道(42.4%)
中小企業の認知度の低さが今後の課題として浮き彫りになった。
主な改正内容:手形廃止と価格協議の義務化
認知度の高い改正内容は以下のとおりです。
-
「約束手形での支払いの禁止」:87.0%
-
「協議を行わない代金決定の禁止」:85.4%
-
「従業員基準の追加」:65.7%
-
「運送委託取引の追加」:63.5%
-
「面的執行の強化」:51.8%
特に手形廃止は、2021年の成長戦略実行計画や全国銀行協会の2026年度末までに手形ゼロにする行動目標などと連動しており、関心が高いです。
受注者の44.5%がプラス影響を見込む
改正されることを知っていると回答した受注者のうち最も期待している主なプラス影響は次のとおりです。
-
「資金繰りの安定」:29.8%
-
「収益の安定化」:21.9%
※この2項目の合計は51.7%にのぼります。 - 「発注者とのより対等な立場での取引関係」:18.7%
- 「発注者側のコンプライアンス意識が高まる」:17.3%
一方、懸念点も明らかです。
-
「書類作成・監査対応の負担増」:23.3%
-
「原価割れによる利益の圧迫」:21.1%
-
「手終了負担を強いられる」:14.3%
-
「既存取引の喪失の可能性」:13.7%
-
「業務フローの変更」:10.5%
発注者の対応:管理負担・利益圧迫への懸念
改正されることを知っていると回答した発注者のうち最も期待している主なプラス影響は次のとおりです。
-
「長期的なパートナーシップ」:51.5%
-
「コンプライアンス強化」:29.0%
- 「ブランド価値の向上」:11.5%
一方、懸念点も明らかです。
-
「利益の圧迫」:23.3%
-
「研修負担の増加」:21.2%
-
「資金繰り悪化」:19.4%
-
「システム対応」:12.8%
発注者は従業員基準の管理や委託先の情報把握に実務負担が増す見込みです。
不公正な慣行:価格据え置きや納期変更が上位
企業が不公正と感じている取引慣行は以下のとおりです。
-
「一方的な価格決定・据え置き」:42.0%(運輸業では50.0%)
-
「曖昧な納期・急な変更」:29.5%
-
「長期手形・割引手数料の負担」:24.8%
-
「不当な減額・返品」:20.8%
- 「発注者からの過度な情報開示要求」:17%
- 「契約書面の不交付、または記載内容の不備」:12.5%
- 「運送事業者の無償での荷待ちや荷役作業」:10.9%
- 「多重下請けによる利益の目減り」:10.2%
- 「特に問題は感じない」:21.3%
不公正な慣行の是正
「改正が不公正な取引慣行の是正に寄与する」と回答した企業は62.1%です。
-
「非常に寄与する」:6.8%
-
「ある程度寄与する」:55.3%
- 「どちらともいえない」:29.9%
法改正以外の必要事項:「企業文化の改革」が最多
法改正以外に必要とされる施策は以下の通りです。
-
「発注者の企業文化・意識改革」:41.2%
-
「政府・行政の指導・監督強化」:41.0%
-
「業界団体のガイドライン策定」:30.6%
-
「受発注間のコミュニケーション強化」:30.5%
- 「受注者側の価格交渉力強化支援」:22.3%
- 「デジタル技術を活用した契約・取引プロセスの透明化」:14.1%
- 「法の適用範囲のさらなる拡大」:11.0%
- 「多重下請けの是正に向けた具体的な取り組み」:10.4%
- 「その他」:4.3%
- 「特に必要だと感じることはない」:9.4%
まとめ:運用対応と実務負担の増加に備えが必要
改正下請法は、中小企業がコスト上昇分を価格に転嫁しやすくし、支払い期間を短縮することを目的としています。今回の改正で運送業者なども対象に加わり、中小企業の取引改善を目指しています。
この法律の認知度はまだ低く、特に中小企業では浸透が不十分です。法律の情報を「届ける」だけでなく「理解させる」ための周知活動と、行政や専門家による支援が不可欠です。
多くの企業が法改正により資金繰りや収益の改善を期待しています。これは、不公平な取引慣行を是正し、公正な取引関係を築くための法的インフラとして注目されています。
施行まで半年を切り、業務負担増への懸念もあります。監督官庁や金融機関などの連携により、サプライチェーン全体の資金効率を高め、適正な価格転嫁と取引適正化が進むことで、賃上げへの道筋が開けることが期待されます。
参考サイト
・『(令和7年5月16日)「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」の成立について』
関連記事