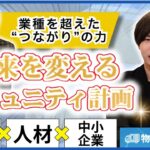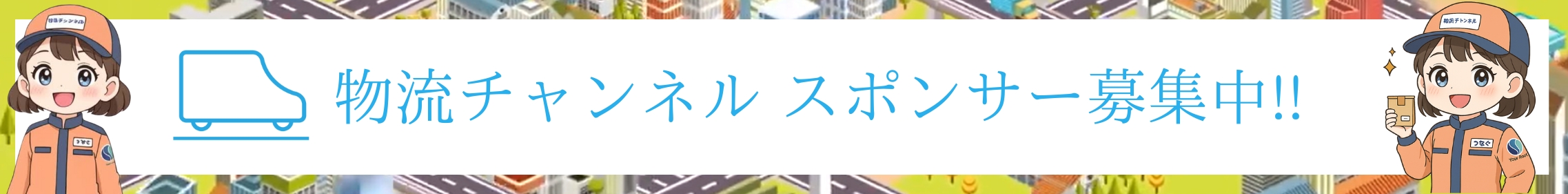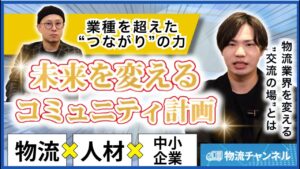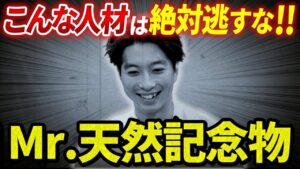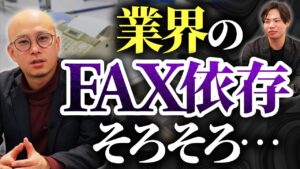流通経済研究所が宮崎発で実証実験 農産物と日用雑貨の共同物流でCO2 31%削減達成
農産物と加工食品・日用雑貨の連携で成果
流通経済研究所は2025年2月、農産物出荷データと加工食品・日用雑貨の物流情報を連携させた共同物流実証において、温室効果ガスの大幅削減やドライバーの労働環境改善など、多角的な効果が確認されました。
背景と目的:2024年問題と物流課題への対応
国内の農産物・食品輸送の約98%がトラック輸送が担う中、「2024年問題」(ドライバーの時間外労働規制強化)とドライバー不足が深刻化しています。加えて、復路の空車問題や物流情報の非共有も物流業界の深刻な課題となっています。
流通経済研究所は、スマートフードチェーンプラットフォーム「ukabis」と「リテール物流・商流基盤」を連携させた共同物流の仕組みを構築し、その効果を検証しました。また、東京方面から九州各地への加工食品や日用雑貨の物流は福岡県に集中している現状における災害時の経路遮断リスクに対し、新たに整備された宮崎県えびの市の物流拠点を活用した代替経路の有効性も併せて検証しました。
実証概要
実証期間:2025年2月2日から2月8日
往路: 宮崎港 → 神戸港 → 東京(農産物輸送)
復路:東京 → 大阪 → 神戸港 → 宮崎港 →宮崎県 えびの市 → (福岡・鹿児島)(日用雑貨輸送)
従来空車になっていた農産物輸送の帰路に日用雑貨を積載することで車両稼働率を向上させました。
実証結果:CO2削減とドライバー負担軽減に効果
実証実験では、以下のような成果が確認されました。
- 積載率と運行スケジュールの安定化: 「ukabis」とリテール物流・商流基盤の連携により、従来不安定だった宮崎方面への帰り荷(戻り便)日用雑貨品の安定を確保しました。これにより、実車率向上と安定運行スケジュールの設定が期待できます。
- CO2排出量とドライバー拘束時間削減: フェリーを活用した往復輸送により、総運行のCO2排出量を現状比約31%削減(4.22tから2.93t)する可能性が示されました。また、ドライバー拘束時間についても現状比約22%〜33%(約1日から2日)短縮できる見込みです。
- 荷役時間とドライバー負担軽減: 復路日用雑貨品の完全パレット輸送により、バラ積み青果物と比較して荷役時間が約83%短縮されることが確認されました。これにより、ドライバーの労働負担が大幅軽減され、今後の青果物パレット化でさらなる改善が期待されます。
- 新たな輸送経路の確保と災害対応力強化: 福岡経由陸路にほぼ依存している東京方面から九州各地への輸送に対し、宮崎港経由・宮崎県えびの市の物流拠点を活用する新経路を確保しました。これにより、既存経路への依存度を減らし、異業種との共同輸送や災害時の物資輸送の対応力強化につながる可能性を示した。
今後の課題と展望:情報共有と多角的な連携が鍵
青果物パレット輸送に切り替えに伴う積載率低下やコスト面が今後の課題です。これを解決し、物流を最適化するためには、ダブル連結トラックなどによる長距離幹線輸送の効率向上と、ラストワンマイル配送による柔軟性確保の効果的な導入が必要です。実現には、幹線輸送と地域配送の接点での荷物切り替え地点・タイミングで・モードの把握と調整する必要があり、そのためには行政・企業・異業種間での情報共有と連携が不可欠です。
今回の実証により、物流情報の連携体制の強化の重要性が再確認されました。今後は得られた成果と課題を踏まえ、本仕組みの社会実装と展開を進めていきます。具体的には、地域や季節による流動性が高い農産物と、安定した加工食品や日用雑貨といった工業製品との連携強化、他業種・他拠点を含めた共同物流のスキームを拡大、複数荷主間での物流情報の連携をさらに強化することで、往復輸送や共同物流機会を増やし、日本全体の物流最適化を進める予定です。
九州地域の物流ネットワークの多元化と安定性向上により、災害対応可能なBCP(事業継続計画)機能強化を目指します。これと合わせて、鉄道・フェリー活用によるモーダルシフト推進とCO2排出量の削減を通じ、脱炭素社会実現にも貢献していきます。
参考サイト