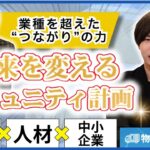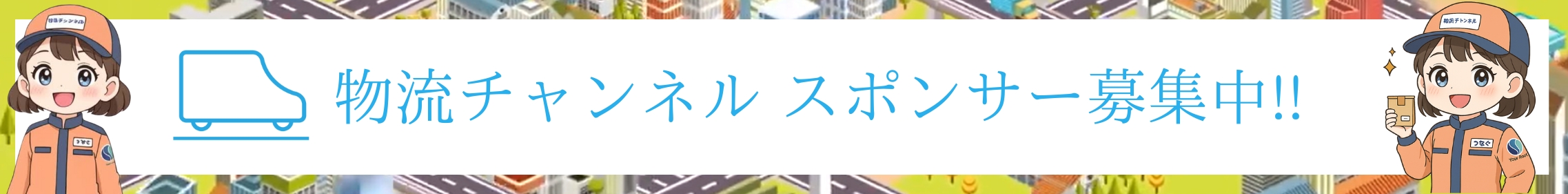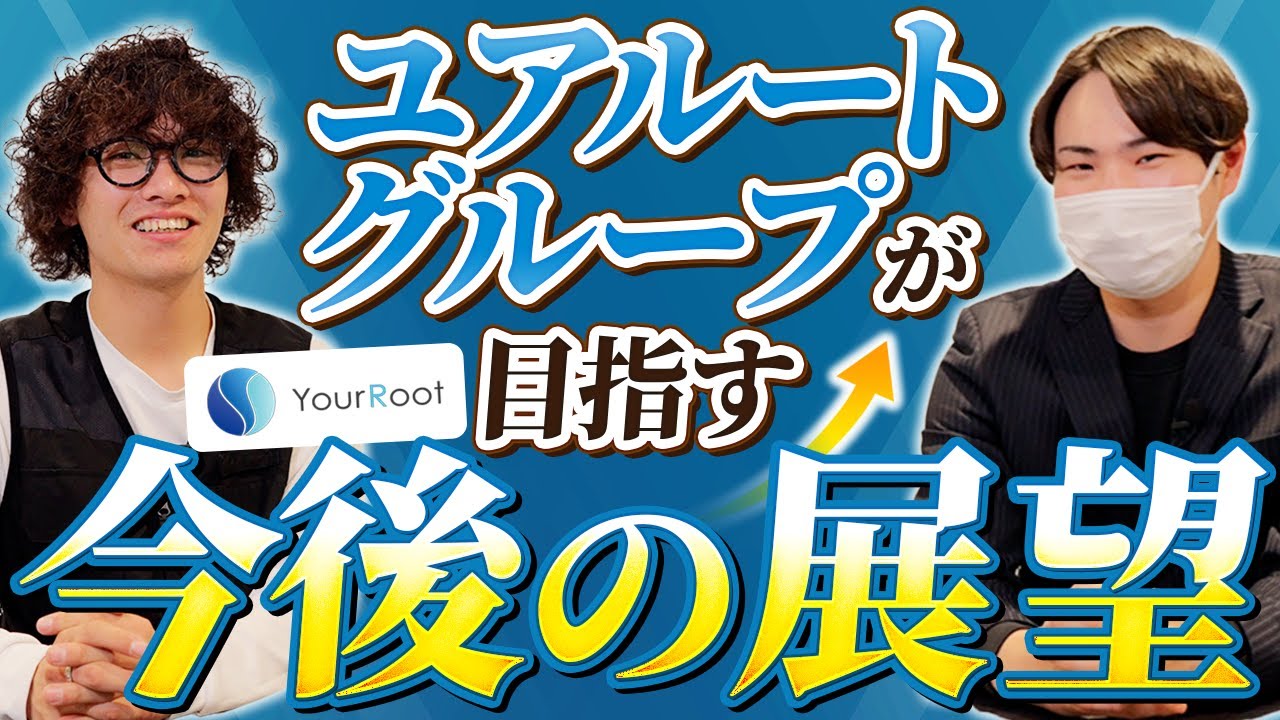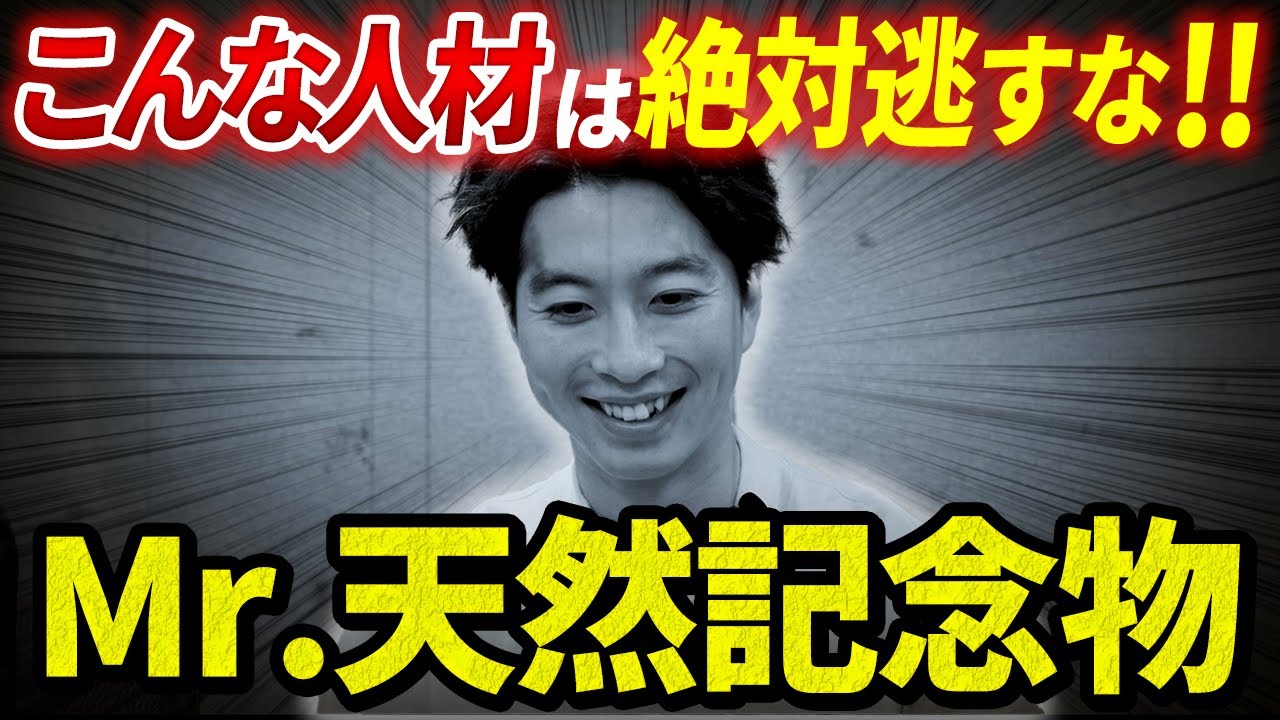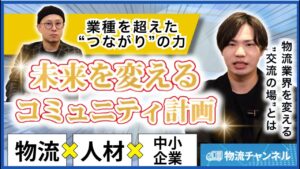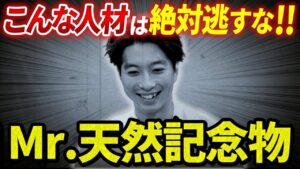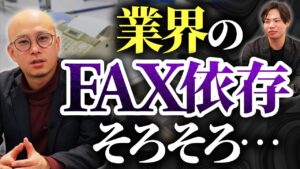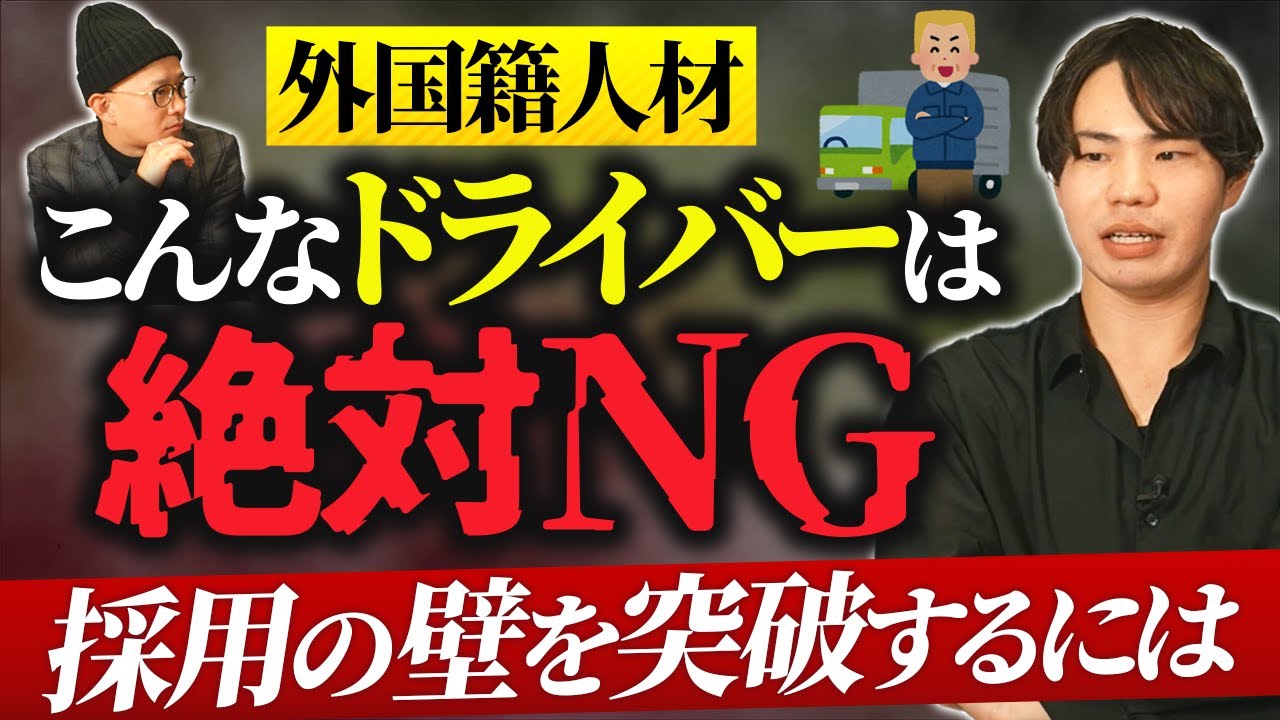
【軽貨物】外国籍ドライバー事情と引き抜き問題|vol.138
物流業界の経営者や業界従事者に有益情報を発信するお役立ちメディア物流チャンネル。vol.138は『【軽貨物】外国籍ドライバー事情と引き抜き問題】』です。
- 国内人材の減少→外国籍ドライバーの活用が不可欠となっている
- 言語の壁や安全性、品質保証の取り組み→課題として浮上している
- 採用プロセスの工夫や引抜き問題への対策→業界全体の成長に繋がる
Youtube動画で見たい方はコチラからもご覧いただけます!
※本人の発言と実際の記載が完全一致しない場合もございます。予めご了承ください。
目次
軽貨物業界の現状|人手不足の深刻化
現代の物流業界は、少子高齢化の影響や労働環境の変化により、従来の働き手では対応しきれない深刻な人手不足に直面しています。
特に軽貨物事業者においては、日本人ドライバーの減少が顕著であり、荷主からのプレッシャーも増大しています。
こうした背景から、企業は「外国籍ドライバー」の採用を積極化させ、異なる文化や言語を持った人材を受け入れることで事業継続を模索しています。
しかし、単に人手を補うだけではなく、信頼性や安全性の確保が最重要課題として浮かび上がってきます。業界関係者からは「日本語が十分に話せない場合はNG」といった声や、安全面での懸念が率直にあがっています。
外国籍ドライバー採用|実態とその課題
外国籍ドライバー採用にあたっては以下のような2つの課題が指摘されています。
- 言語の壁
- 採用プロセスの厳格化
それぞれ詳しくみていきましょう。
課題1|言語の壁
日常会話は可能でも、書類の読み書きに支障があったり、検定基準(たとえばN4レベルなど)を満たしていても、実際のコミュニケーションに不安があるケースが見受けられます。
課題2|採用プロセスの厳格化
荷主の要望を受け、ドライバーの質を保証するために、面談やオーディション形式の選考が行われています。未経験者の場合、企業側からは「一定の経験や判断ができる人材でないと難しい」との意見も多くあります。
実際、軽貨物事業者は「負担軽減のために、積極的に外国籍の人材を採用したい」という考えと、「コミュニケーション不足などで安全性に不安がある」という対立する意見が共存しており、そのバランスをどう取るかが今後の大きなテーマとなっています。
工夫|品質保証と採用プロセス
品質を保証するため、現場では複数人数での面談や厳しい審査が行われています。具体的には、以下の3つが挙げられています。
- 複数(例:3名)での面談体制
- 研修制度の強化
- 荷主側との連携
それぞれ詳しくみていきましょう。
具体例1|複数(例:3名)での面談体制
面談担当者と、場合によっては複数の評価者が同席し、ドライバーの人柄やスキルを総合的に判断することで、採用時のリスクを低減しています。
具体例2|研修制度の強化
仮に未経験者や初めて応募する外国籍の方であっても、十分な研修を実施し、業務遂行に必要な知識と技術を習得させる工夫がされています。
具体例3|荷主側との連携
最終的な安全性や品質の保証については、荷主の面談や意見も踏まえて決定されるため、採用決定前に多角的な確認が行われる体制が整えられています。
.png)
引抜き問題と業界内の競争
もう一つの重要な課題として、引抜き問題が挙げられます。以下の2つのような現状があります。
- 引抜き合戦の激化
- 継続的な雇用が困難
それぞれ詳しくみていきましょう。
現状1|引抜き合戦の激化
ある企業が採用した優秀な外国籍ドライバーが、他の物流会社からも同様の声がかかる事例が存在し、結果として引抜き合戦が激化している。
現状2|継続的な雇用が困難
一度採用したドライバーが、企業間での評価基準やコミュニケーションの違いから、継続的な雇用が難しくなるリスクがある。
このような引抜き問題は、採用側だけでなく、業界全体の信頼性を揺るがす大きな要因です。
企業は、単に人を集めるだけでなく、採用後のフォロー体制やキャリアパスの明確化、給与体系の見直しなど、ドライバーが長期にわたって安定して働ける環境作りに努めなければなりません。
外国籍ドライバー活用|未来展望と業界戦略
これからの物流業界は、外国籍ドライバーの採用を通じて、従来の労働環境改革やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進といった大きな転換期に突入しようとしています。具体的には、以下の3つの戦略が欠かせません。
- SNSやオンラインプラットフォームの活用
- グローバル展開のさらなる推進
- 採用後のフォローとキャリアパスの明確化
それぞれ詳しくみていきましょう。
戦略1|SNSやオンラインプラットフォームの活用
YouTubeやその他SNSを通じ、現場のリアルな声や業務の裏側を発信することで、物流業界の魅力や安心感を広く伝え、優秀な人材の獲得につながるでしょう。
戦略2|グローバル展開のさらなる推進
日本独自の物流技術やノウハウを海外にも展開し、外国人労働者の活用だけでなく、国際競争力の向上を目指し、また、海外からの技術導入や協力体制が、業界全体の発展に寄与するでしょう。
戦略3|採用後のフォローとキャリアパスの明確化
採用の段階で厳格な審査を実施するとともに、研修制度やキャリアアップの仕組みを整備することで、採用したドライバーが安心して長く働ける環境を提供します。
これらの戦略が実現すれば、外国籍ドライバーの採用は単なる「人手不足」の穴埋めではなく、業界全体の信頼性・安全性の向上、ひいては物流市場の成長へと直結していくことでしょう。
まとめ
軽貨物業界では、日本人ドライバーの減少に伴い、外国籍ドライバーの採用が急務となっています。しかし、採用にあたっては「言語の壁」や「品質保証の難しさ」、さらに引抜き問題といった複数の課題が存在します。
企業側は、複数の面談体制や充実した研修制度、荷主との連携を通じて、信頼できるドライバーの確保に努めるとともに、業界全体での環境整備と価値向上を図る必要があります。
今後、SNSを活用した情報発信やグローバルな視点での採用戦略により、外国籍ドライバーを含む多様な人材が活躍できる物流業界へと変革していくことが期待されます。これにより、物流業界は従来の「危うい現状」から脱却し、さらなる成長と安定を実現する重要な転換期を迎えることでしょう。
> 無料資料請求
> スポンサー募集の詳細ページ
Youtube動画で見たい方はコチラからもご覧いただけます!
※本人の発言と実際の記載が完全一致しない場合もございます。予めご了承ください。