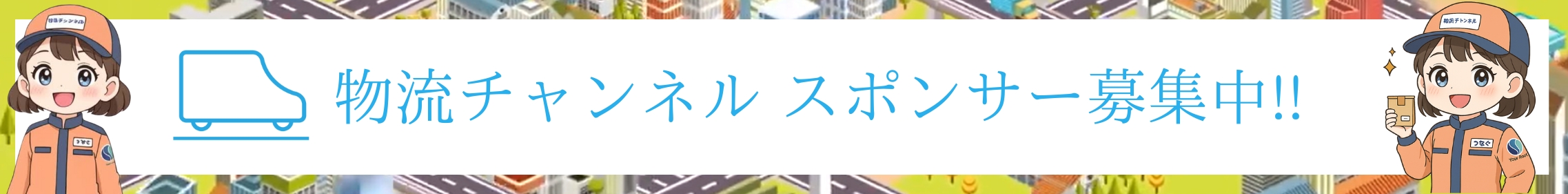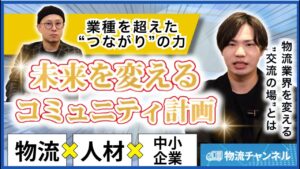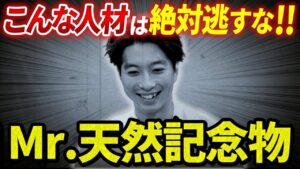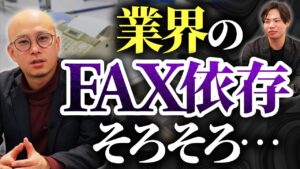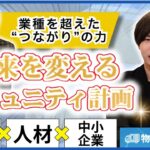

トラックドライバーの睡眠時間は?快眠術&仮眠法を紹介!
トラックドライバーにとって「睡眠時間の確保と質の向上」は、命を守る最重要課題です。
本記事では、拘束時間や休息時間のルールをふまえつつ、事故リスクを減らすための仮眠法や快眠グッズ、現場で使える実践対策を紹介しています。
睡眠不足による集中力低下・体調不良・事故リスクに不安を抱えるトラック運転手の方へ、90分仮眠法やおすすめグッズをチェックし、安心・安全な運転環境を手に入れましょう!
目次
トラックドライバーの平均的な睡眠時間
トラックドライバーは、長時間の拘束や不規則な勤務時間により慢性的な睡眠不足に陥りやすいです。ここでは、トラックドライバーの平均的な睡眠時間について紹介します。
トラックドライバーの多くは、1日あたりの平均睡眠時間が6時間未満とされており、一般的なオフィスワーカーと比較して明らかに短い傾向があります。これは長時間の拘束や不規則な勤務時間が主な原因とされ、特に夜間の長距離運行を担うドライバーは、慢性的な睡眠不足に陥りやすくなっています。
例えば、日中に地場配送を行うドライバーと比較すると、夜間走行の多い長距離ドライバーは仮眠のタイミングが限られるため、十分な休息を取れないまま連続運転に入るケースも少なくありません。
こうした現状を踏まえ、まずは自身の平均睡眠時間を把握し、適切な対策を取ることが、日々の体調管理と安全運転の第一歩となるでしょう。
トラックドライバーができる睡眠対策・眠気対策
過酷な労働環境でも、安全な運転を維持するには「短時間でも質の高い睡眠」と「効果的な眠気対策」が欠かせません。ここでは、トラックドライバーが今日から実践できる具体的なアプローチを紹介します。
- 90分サイクルを意識して仮眠をとる【睡眠対策】
- 遮音・遮光環境を整えて熟睡する【睡眠対策】
- カフェインをうまく活用する【眠気対策】
- 光と音の刺激を減らして入眠スイッチを入れる【眠気対策】
まずは「90分サイクルを意識して仮眠をとる【睡眠対策】」から見ていきましょう。
1.90分サイクルを意識して仮眠をとる【睡眠対策】
トラックドライバーができる睡眠対策・眠気対策、1つ目は「90分サイクルを意識して仮眠をとる【睡眠対策】」です。
人間の睡眠は90分ごとの周期で深い眠りと浅い眠りを繰り返すとされており、この「90分サイクル」に合わせて仮眠をとることで、目覚めのスッキリ感と集中力の持続が期待できます。
とくに深夜運行や連続運転の合間にこの仮眠法を取り入れることで、疲労の蓄積を防ぎ、事故リスクの低減にもつながる重要な対策です。
2.遮音・遮光環境を整えて熟睡する【睡眠対策】
トラックドライバーができる睡眠対策・眠気対策、2つ目は「遮音・遮光環境を整えて熟睡する【睡眠対策】」です。
仮眠の質を左右するのは「静かで暗い」睡眠環境です。耳栓やアイマスク、遮光カーテンといったグッズを活用することで、トラックの車内でも外部の光や音を遮断し、スムーズな入眠が可能になります。
こうした小さな工夫でも、眠りの質は大きく変わります。数千円の投資が、命を守る快眠環境につながるのです。
3. カフェインをうまく活用する【眠気対策】
トラックドライバーができる睡眠対策・眠気対策、3つ目は「カフェインをうまく活用する【眠気対策】」です。
トラックドライバーにとって、眠気対策の切り札とも言えるのが「コーヒーナップ(Coffee Nap)」です。これは仮眠の直前にカフェインを摂取することで、目覚め後の覚醒効果を最大化するテクニックです。
具体的には、コーヒーを飲んでから20分前後の短時間仮眠を取ると、カフェインの効果がちょうど目覚めのタイミングで現れ、スッキリとした覚醒感を得られます。
ただし、カフェインは就寝前に摂取すると入眠を妨げるため、使用するタイミングが重要です。「午前中の運行前」「午後の眠気が強い時間帯」など、ピンポイントでの活用が理想的です。
4. 光と音の刺激を減らして入眠スイッチを入れる【眠気対策】
トラックドライバーができる睡眠対策・眠気対策、4つ目は「光と音の刺激を減らして入眠スイッチを入れる【眠気対策】」です。
眠気を感じていても、入眠できない要因のひとつが「視覚・聴覚刺激」です。特にスマートフォンの強い光や、ナビ音声・走行音は、脳の覚醒状態を維持してしまいます。そこでおすすめなのが「スマホ断ち」と「静音環境の確保」です。
寝る30分前からスマホや強い光を避け、耳栓やリラックス音楽を使うことで、自然とメラトニンの分泌が促され、スムーズな入眠につながります。すぐできる簡単な工夫こそ、快眠への第一歩です。
トラックドライバーが役立つ睡眠グッズ
トラックドライバーに大切な仮眠は、役立つ睡眠グッズを活用することも大切です。ここでは、役立つ睡眠グッズについて紹介します。
質の高い仮眠には、環境の整備が欠かせません。とくにトラックの車内では、アイマスク・耳栓・ネックピローなど、専用の快眠グッズが非常に効果的です。これらを活用することで、遮光・遮音・体勢の安定が実現でき、限られた時間でもしっかりと休息が取れます。
さらに、夏場の熱気対策には小型扇風機、冬場には毛布や断熱マットなど、季節に応じたグッズ選びも重要です。「自分専用の快眠セット」を用意することで、運行中の睡眠効率が大きく向上します。
トラックドライバーがやりがちな睡眠に関するNG例と対処法
トラックドライバーの中には、誤った方法で仮眠をとってしまい、逆に疲れが取れないというケースもあります。ここでは、よくあるNG行動とその改善法について以下の順番で紹介します。
- 昼夜逆転のまま無理に寝ようとする
- 仮眠を短時間で何度も分ける
まずは、「昼夜逆転のまま無理に寝ようとする」について紹介します。
1.昼夜逆転のまま無理に寝ようとする
トラックドライバーがやりがちな睡眠に関するNG例と対処法、1つ目は「昼夜逆転のまま無理に寝ようとする」です。
不規則な勤務で昼夜が逆転してしまった状態で、無理に「夜に寝なければ」と頑張ると、むしろ入眠しにくくなります。これは体内時計(サーカディアンリズム)に逆らっているからです。
この場合は、無理に夜寝ようとせず、むしろ日中や早朝に仮眠を取る習慣を付けるほうが、自然と深い睡眠に入りやすくなります。
2. 仮眠を短時間で何度も分ける
トラックドライバーがやりがちな睡眠に関するNG例と対処法、2つ目は「仮眠を短時間で何度も分ける」です。
15分、20分といった短い仮眠を何度も取るスタイルは、トータルの睡眠時間を確保しているように見えて、実は睡眠の深さが不足している可能性が高いです。これは、ノンレム睡眠に達する前に目覚めてしまうため、脳の回復が不完全なまま運転を続けることになりかねません。理想は90分仮眠や、せめて30分前後の「パワーナップ」です。
連続した仮眠であれば、より深い休息が得られ、運転中の集中力と反応速度の向上にもつながります。
トラックドライバーが睡眠時間を確保できない場合のリスク
トラックドライバーにとって「睡眠不足」は、単なる体調不良にとどまらず、重大事故の引き金となる深刻なリスクです。交通事故の多くが「漫然運転」や「居眠り運転」といった集中力低下によるものであり、これは睡眠時間の不足が直接的な原因となっています。ここでは、睡眠時間を確保できない場合のリスクについて紹介します。
- 睡眠不足と交通事故の関係
- 長距離・夜間運転がもたらす慢性疲労
- 生活リズムの乱れと健康被害
まずは、「睡眠不足と交通事故の関係」について紹介します。
1. 睡眠不足と交通事故の関係
トラックドライバーが睡眠時間を確保できない場合のリスク、1つ目は「睡眠不足と交通事故の関係」です。
睡眠不足状態の運転は、集中力が続かず判断ミスや反応遅延が増えることで、ブレーキの踏み遅れや車間距離の過小判断といったミスが増え、重大事故につながりやすくなります。
睡眠の確保は単なる健康管理を超えた“義務”といえるレベルです。
2. 長距離・夜間運転がもたらす慢性疲労
トラックドライバーが睡眠時間を確保できない場合のリスク、2つ目は「長距離・夜間運転がもたらす慢性疲労」です。
昼夜逆転のシフトや、500km超の長距離走行などが続くと、身体は疲れが取れないまま「なんとか持ちこたえる」状態が常態化します。これが“慢性疲労”です。毎日しっかり寝ているつもりでも、”疲れが取れた感じがしない”そんな状態に心当たりがある方は要注意。自律神経が乱れ、消化不良・肩こり・頭痛なども引き起こします。
肩こりや頭痛を感じた方は同サイトの、【トラックドライバー】の腰痛・肩こりを和らげる簡単「ストレッチ」を紹介!でも紹介しているので一緒にご確認ください!
3. 生活リズムの乱れと健康被害
トラックドライバーが睡眠時間を確保できない場合のリスク、3つ目は「生活リズムの乱れと健康被害」です。
夜間運行→昼間仮眠→夕方出勤…という生活を続けていると、「朝日を浴びる」「三食を決まった時間に取る」といった基本が崩れます。この生活リズムの乱れは、睡眠ホルモン(メラトニン)の分泌を狂わせ、自律神経失調・メタボ・高血圧・うつ症状といった“目に見えにくい健康被害”を引き起こします。
反対に、就寝・起床時間を固定し、食事・仮眠をルーティン化するだけで「体調が改善した」と感じるドライバーも多く、日常生活の見直しは最も効果的な健康対策です。
トラックドライバーの睡眠時間対策として企業ができること
ドライバーの睡眠確保は、もはや“個人の努力”に任せておくべき課題ではありません。法令上の拘束時間・休息時間の順守だけでなく、企業側が「眠れる環境づくり」を支援することが、事故防止・労働力確保・企業価値向上すべてにつながります。ここでは、企業ができる支援策について紹介します。
- 健康状態確認の仕組化
- 睡眠時間に関するアンケートの実施
- 稼働スケジュールの管理
- 休憩のルール化
まずは、「健康状態確認の仕組化」について紹介します。
1. 健康状態確認の仕組化
トラックドライバーの睡眠時間対策として企業ができること、1つ目は「健康状態確認の仕組化」です。
点呼時に「体調どう?眠れてる?」と声をかけるだけで、異変の兆候をキャッチできるケースがあります。睡眠不足や体調不良はドライバー本人が自覚しにくいため、管理者による第三者チェックが欠かせません。
体調チェックは単なるルーティンではなく、命を守るための最前線なのです。
2. 睡眠時間に関するアンケートの実施
トラックドライバーの睡眠時間対策として企業ができること、2つ目は「睡眠時間に関するアンケートの実施」です。
そもそも社員がどれくらい寝ているかを把握していない企業も多いのが現状です。年に1〜2回、睡眠時間・睡眠の質・眠気の頻度などをアンケート形式で可視化することで、部署やシフトごとの問題点が明らかになります。
視化 → 施策 → 改善 のサイクルを作るためにも、アンケートは第一歩です。
3. 稼働スケジュールの管理
トラックドライバーの睡眠時間対策として企業ができること、3つ目は「稼働スケジュールの管理」です。
「利益を優先しすぎてドライバーに無理をさせてしまった」そんな企業が、今こそ見直すべきなのが勤務スケジュールです。過度な連勤や12時間超の勤務が常態化している場合は、法令遵守以前に健康と命が危険にさらされます。
週ごとの稼働調整や、夜勤明けの翌日休み制度など、無理のない運行計画が結果的に事故リスク・離職率を下げ、企業の持続性を高めます。
4. 休憩のルール化
トラックドライバーの睡眠時間対策として企業ができること、4つ目は「休憩のルール化」です。
「好きなタイミングで仮眠していいよ」では、どうしても睡眠が後回しにされてしまいがちです。これを防ぐには、法定休憩とは別に「○時間運転したら必ず○分の仮眠を取る」といった“明文化されたルール”が効果的です。
明確なルールが安全文化の土台になります。
トラックドライバーの睡眠時間を管理することも重要
トラックドライバーの睡眠は、本人の健康維持だけでなく「輸送の安全性」と「企業の信頼」にも直結する重要なテーマです。そのためには、ドライバー個人に対策を任せきりにするのではなく、管理者・企業側も一体となって「眠れる仕組み」を整えることが不可欠です。
運転日誌や体調記録を習慣化することで、「自分の睡眠リズムと仕事の相性」に気づきやすくなり、セルフマネジメントの意識向上にもつながります。
つまり、安全な物流を支えるためには、「安全運転=よく眠ること」という共通認識を持ち、企業とドライバーが共に眠りと向き合う体制づくりが何よりも大切なのです。管理の強化ではなく、信頼と安心を育む“対話”が、明日の無事故運行をつくります。